
2024.05.31
- カンファレンス
電気料金高騰の中、「電気代0円家電」にチャレンジ 社会課題を「バッテリー」で解決へ。家電シリーズ「ELEIN」が登場!
- 家庭機器事業部
阪神・淡路大震災から30年。神戸・松蔭中学校の防災授業で山善の「防災バッグ30」が取り入れられた理由
2025.03.21
能登半島地震から1年、阪神・淡路大震災から30年。南海トラフ地震の発生も予測されるなか、いつ、どこで地震がおこっても不思議ではないのが、地震大国日本の日常だ。突然やってくる地震に対して、誰もができる唯一の対策が「備え」。山善の「防災バッグ30」がヒットした背景には、この高まる危機意識が考えられるだろう。
そうした中、「防災バッグ30」を子どもたちの防災学習のツールとして活用している事例が兵庫の神戸市にある。2025年2月17日に行われた松蔭中学校と山善との連携授業についてレポートする。
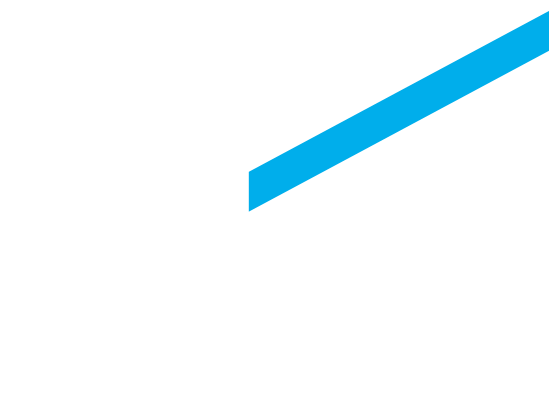
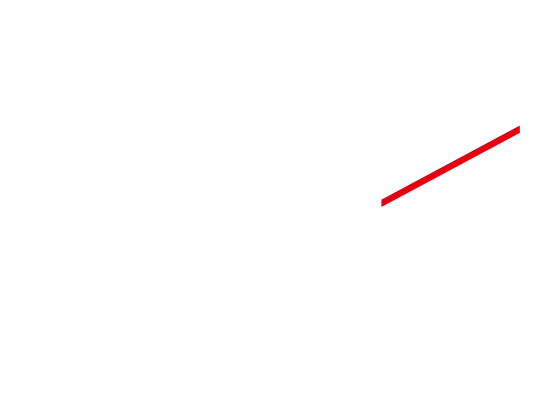
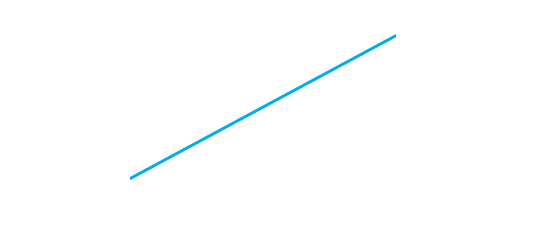
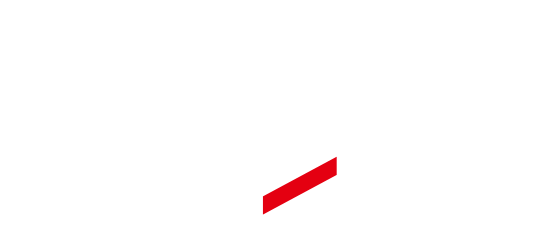
兵庫県神戸市、三ノ宮駅から山手に車で10分ほど行った閑静な住宅街にある松蔭中学校。1892年にイギリス国教会の宣教団体S.P.G.のH・J・フォスらによって設立された、130年の歴史を誇る学校だ。山善の「防災バッグ30」を使った防災授業を受けるのは、グローバル・ストリームコース1年生の生徒たち。商品の開発者で、防災士の資格を持つ山善の 家庭機器事業部商品企画4部 部長、小浜成章(こはま なるあき)とともに授業前の教室を訪れると、友達と話しながら準備をするにぎやかな子どもたちの声が響いていた。
「防災バッグ30」は、危険から逃れて命を守るための一時避難に必要な「2WAY懐中電灯」「ラバー手袋」など、合計30点が入っている。だが、バッグにはあえて余白を残しており、購入者が必要だと思うものを入れて完成させることを提案している。小浜曰く、“不完全なバッグ”だ。「これは1人1個ずつ用意していただきたいんです。基本的なアイテムは揃っていますので、ここに季節や年齢などに合わせたアイテムを追加して、自分の防災バッグを完成させてください」と小浜は話す。
この「自分で追加して完成させる」という点に着目したのが、松蔭中学校の篠原弘樹(しのはら ひろき)先生。「神戸ですから、被災者の方のお話を聞いたり、防災センターを訪ねたりと、震災についての学習はかなりやってきました。ですがさらに、自分で主体的に考えて災害に備えようという気持ちが芽生えるようにできないかと考えていた時に、この『防災バッグ30』を知りました」。そこで2021年に、「『防災バッグ30』にもう一つ加えるなら何か」を生徒たち自らで考える授業を実施。これを山善に連絡したところ、小浜との連携が実現し、5回目となる今年は小浜が初めて学校を訪れて、教室での授業に参加した。
授業は山善の会社紹介と小浜の自己紹介からスタート。小浜は防災士の資格を取得したエピソードとして、自身の出身地で消防団として活動していた際、高齢者が多く、防災グッズの準備が不足しがちなことを痛感したことを交え、「防災バッグ30」の開発に取り組んだ経緯を話した。
続いていよいよ生徒たちのプレゼンタイム。まずは前半グループから1人ずつ前に出て、スライドを映しながら「私が入れるのは〇〇です。なぜなら……」と説明が始まった。
「冷え性なので靴下を入れます。」
「スマホが使えなくても安心できるように、家族の電話番号や集合場所など、重要な情報を書いたメモです。」
「デンタルリンス(液体ハミガキ)を加えたいです。災害では、口の中を十分にすすぐ水がないかもしれません。これは液体で口の中をすすげて、歯磨きにもなります。磨いた後にミントの味ですっきりとした気持ちになれます。」
「生理用品を入れます。生理時に使えるのはもちろん、吸収力が高くて面積が広いから、血を止めるのにも使えます。」
「伸縮性のある包帯を入れようと思います。細長くしたらロープの代わりになって、避難所で物をまとめたりもできます。」
ここまで発表すると生徒たちはグループに分かれて、「今のプレゼンのなかから、防災バッグにあと一つ入れるとしたら何を選ぶか」をディスカッション。すると「包帯です。靴下もいいなと思ったけど、包帯も靴下代わりになると思って」「虫歯になるといけないからデンタルリンスです」と他者のアイデアを取り入れたさまざまな意見が。生徒たちの発表を受けて小浜も「防寒はいま入っている商品で代用できるものがありますね。私が防寒面を考えてあえて足すとしたら下着かな」「液体ハミガキも必要ですね。災害の時は水がないことが多いので、歯磨きの時に水を使えないこともあると思います。いいポイントに気づきましたね。その視点で今後も考えてください」などとアドバイスを行った。
後半グループの発表では「正確な情報を入手でき、安否確認にも役立つラジオを入れたい」、「情報収集するには、丈夫で電池だけで動く電池式ラジオ」、「家族写真は見ているだけで安心できて、家族とはぐれたとき探すのも役立つ」、「体を温めることができ、使った後には消臭剤にもなるカイロ」、「汚物処理や応急処置にも使えるおむつ」、「生理用品は止血や何かこぼれたときに拭いたりするのにも使えます」というアイデアが出た。
小浜も「私もこれを入れようか悩んだんですよ」と鋭いアイデアに感心しきり。プレゼンとディスカッションを繰り返すことで、何が必要か深く考え、迷い、答えをひねり出す。この授業で大切にしていることが、自分事として捉えて考えるこのプロセスだ。
「大人には思い浮かばないような、中学生ならではの自由な発想がよかったと思います。これから先も、防災について勉強するとき、柔軟に、いろんなアイデアを出してほしい。この授業をきっかけに、家族、周りの人を含めて防災意識を高めてほしいと思います。本当にありがとうございました」と、最後に全体を振り返った感想を小浜が生徒に伝えた。
そしてこの日はさらに、山善の商品「サッと簡単トイレ」で使用する凝固剤の実演と、簡易トイレの組み立て体験を用意。
小浜が青い液体が入ったカップを生徒たちに見せて、「大人が1回で用を足す尿の量は300mlです。これに凝固剤を入れますが、どのくらいの時間でこれが固まると思いますか?」と質問。「10秒?」「1秒」「1分?」と生徒たちは想像がつかない様子。実際にやってみると、30秒ほどでゼリー状に。「固まってきてる!」「面白い!」と生徒たちから驚きの声が上がった。
続いて、薄くコンパクトにたたまれたプラスチック素材の簡易トイレが登場。小浜が組み立てると、わずか5秒程度で完成。生徒たちも簡単に組み立てることができ、座ってみる生徒も。しかし、反対に元の形に戻すのは、コツがいるようで時間がかかる……。これもやってみなければわからない体験の一つだ。「今まで簡易トイレは段ボール製が多かったのですが、組み立てるのに時間がかかるうえ、洗えませんでした。湿気でふにゃふにゃになることもなく、繰り返し洗って使うことができます。トイレは一番ストレスがたまりますからね」との小浜の話に、生徒たちも聞き入るばかり。
授業の終わりには、今日印象に残ったことを生徒たちが発表。「カイロに消臭効果があるとは知らなかった」「地震のときに初めてではなく、日常的に確認しておくことが大切」など、生徒たちにとって学びの多い時間になったよう。最後に山善から「防災バック30」を生徒たちにプレゼントして、この日の授業は終了した。
「体験してみないとわからないと生徒たちが実感してくれたことがうれしかった。生徒さんたちのアイデアを取り入れた新たな防災バッグを開発できたらいいなと思います」と小浜。篠原先生も「高校生でもう一回、こういった防災授業をやるともっと防災意識が深まると思います。生徒が自分たちで考えて話し合っている姿を見ると、やってよかったと実感します」と手ごたえを感じていた。
いざという時に、どういう行動ができるのかは、「モノ」と「体験」が揃い、日ごろから考えて備えておくことが必要だと教えてくれたこの授業。生徒たちの防災意識の高まりに、“不完全なバッグ”が役立っている。
防災バッグ30はコチラ:https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00005070
サッと簡単トイレ<折りたたみ式>はコチラ:https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009144