
2021.02.01
- 社員インタビュー
群馬に「杉田商店」あり!生粋の負けず嫌い 機工・杉田流の「提案営業」と「エリア戦略」
- 営業社員
- ツール&エンジニアリング事業部
【2030年】製造業が抱える課題と必要な対応を解説
2024.10.18
労働人口が大幅に減少する2030年問題にともない、製造業が抱える課題による影響もピークを迎えると予測されています。今回は、2030年に製造業が抱えるであろう4つの課題に焦点を当て、講じるべき対策について解説します。
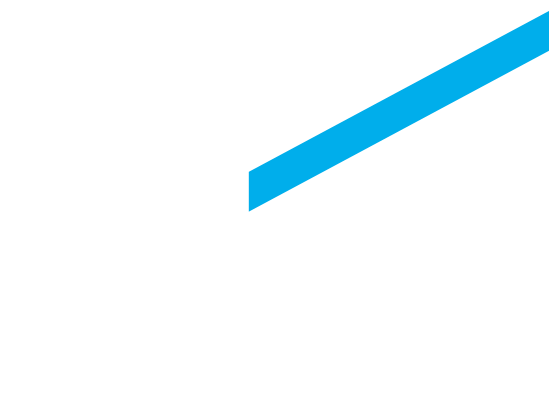
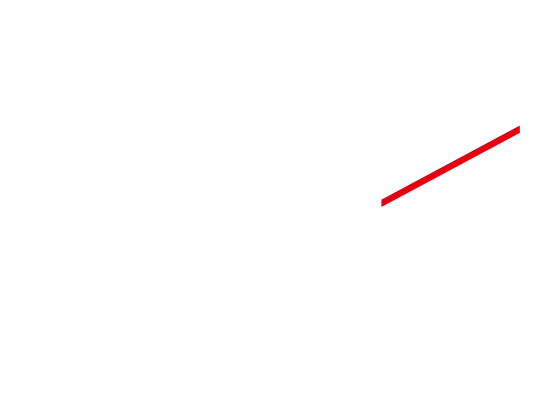
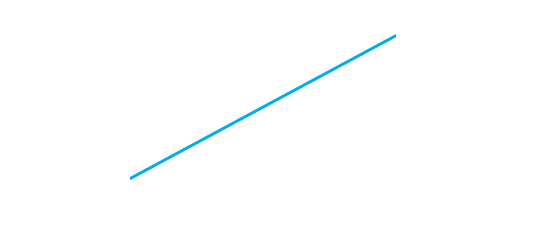
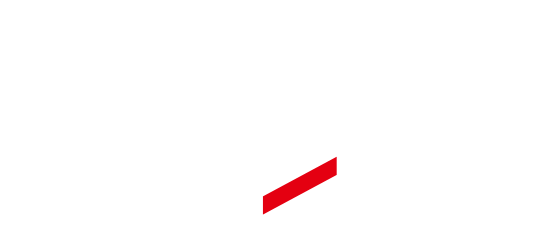
ここでは、2030年に製造業が対策を迫られることが予測される課題の代表例について、4つの観点から紹介します。
現在も多くの企業が悩まされている人手不足と従業員の高齢化は、2030年に向けて、ますます深刻化していくと考えられます。
経済産業省によると、2023年の中小企業における製造業の従業員数過不足DIはマイナス20.4と、コロナ禍以前(2019年)よりも人手不足感は増している状況です。
また、34歳以下の若年就業者が占める割合は、2002年と比較して6.9ポイントも減少しています。これに対し、65歳以上の高齢就業者数が占める割合は、3.6ポイント増加しているのが現状です。
出典:経済産業省「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」
今後、少子高齢化は進む一方であることを踏まえると、製造業における人手不足と従業員の高齢化への対策は欠かせないといえます。
日本の製造業における強みのひとつである技術力の継承がうまくいっていないことも2030年に向けて対策が求められる課題です。ベテラン従業員の退職時に次の世代にスキルやノウハウがきちんと引き継げていない結果、技術力が低下してしまったという事例が散見されます。
経済産業省の調査においても、製造業の企業の61.8%が「指導する人材が不足している」、46.1%が「人材育成を行う時間がない」と回答しています。この結果からも、技術継承の寸断の課題が深刻であり、本腰を入れた対策が必要であることがうかがえるでしょう。
出典:経済産業省「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」
IT化・DX推進の遅れも製造業が2030年に向けて対策を検討すべき課題といえます。IT化・DXが進むことで、「技術の継承がしやすくなる」「人手不足による負担の軽減につながる」といった効果を見込めるためです。
IT化・DX推進をする上では、デジタル人材の確保などに代表される体制や環境の整備が欠かせません。しかし、デジタル人材の確保はハードルが高いのも実情です。総務省の調査においても、実に41.7%もの企業がデジタル人材の不足を課題としてあげています。
出典:総務省「令和5年版情報通信白書」
製造業においては、国際競争力の低下への対応を検討していく必要があります。デジタル化が進んだことで、これまで製造業の競争力が高くなかった国々でも、低価格で安定して製品生産できるようになってきたためです。
グローバル化の進展にともない、低価格化が進む諸外国の製品と競争を強いられるようになった結果、日本の製造業は競争力が伸び悩みつつあります。また、近年では製品のトレンドの移り変わりが早くなっているのも特徴です。短いサイクルでの開発に対応できる体制を整えることも求められつつあります。
製造業が抱える4つの課題を踏まえて、2030年に向けて効果的な対応例を紹介します。
人手不足や従業員の高齢化の課題に対処し、スムーズにデジタル化を進められる体制を構築するためには、優秀な人材の確保・流動化対策が必要です。
とはいえ、人材の確保がスムーズに進まない場合も多いでしょう。そこで検討したいのが、外国人技術者や派遣社員など幅広い人材の登用です。特に派遣社員での雇用であれば、繁忙期だけ人員を増やすといった運用もできるため、人件費をはじめとするコストの増加をある程度抑えられます。
また、採用の間口を広げるだけでなく、定着させるための施策もあわせて行いましょう。研修制度を充実させて人材育成やスキルアップに力を入れるとともに、福利厚生や待遇を充実させると効果的です。
ナレッジマネジメントとは、各従業員が現場での業務経験などを通して身に付けた技術や知見を、組織全体で使えるように標準化させ活用する経営手法のことです。知識やスキル・ノウハウの属人化を防ぎ、組織全体のスキルアップを図れます。
ナレッジを共有しておくと、新たに採用された従業員であってもすぐにノウハウを学ぶことができるため、人材の流動化対策としても有効です。また、技術や知見が誰にでもわかりやすいナレッジとして整理されていると、研修の教材として活用できます。人材育成に注力していきたい場合にも役立てられます。
パンデミックの発生・自然災害・貿易摩擦・軍事衝突など、有事の際にも安定して原料の調達や製品の製造が継続できるサプライチェーンの再構築が欠かせません。
コロナ禍や自然災害などの発生にともない、サプライチェーンの脆弱性が露呈した企業は多いでしょう。今後も異常事態が発生するリスクは、常につきまといます。安定した供給を維持するには、供給網全体について緊急時の影響がどの程度あるのかを可視化し、適切な対策を取ることが必要です。
複数の供給元を確保する、AIによるリスク予測の実施や在庫管理の効率化など、自社の環境に適した対策の導入を検討しましょう。
製造業のサプライチェーンについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
「製造業におけるサプライチェーンとは?課題と最適化する方法を解説」
IT人材の育成とデジタルツールの導入を進めると、IT化・DX推進の遅れや人手不足、国際競争力低下への対策に役立ちます。
AI搭載ロボットによる一部業務の代替、IoT機器による制御によって効率化を見込めるためです。経済産業省の調査においても、デジタル技術の活用が進んだ企業の多くが品質向上やコスト削減を実感しています。また、業務効率化が進むことで、人手不足の解消や労働時間の短縮などの効果も期待できます。
出典:経済産業省「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」
「製造業のデジタル化を進めたいけれど、どのように進めるべきか悩んでいる」という場合は、製造現場に特化したデジタルサービス「ゲンバト」をお試しください。
ゲンバトは、設備管理・図面管理・不良管理・日報管理・QC文書管理に加えて、案件の発注・受注ができるエンムスビなど、多彩なサービスを展開しています。ニーズに合わせて柔軟に活用できるので、コストを抑えて狙った効果を得られるでしょう。
例えば、図面管理や設備管理のデジタル化による生産効率アップやコスト削減により、ナレッジマネジメントに割く時間を捻出できるようになります。また、製造業に関わるさまざまな企業が集まるプラットフォームであるため、新たな取引先を開拓したい場合やサプライチェーンを強化したい場合にも最適です。
製造業で2030年に向けて対策が必要な課題として、人手不足と従業員の高齢化・技術継承の寸断・DX推進の遅れなどがあげられます。優秀な人材の確保・流動化対策やナレッジマネジメントの実施など、今回ご紹介した対策を検討し、将来にわたって持続可能な基盤を整えましょう。