
2025.12.19
- 社員インタビュー
ASEAN最大級の経済大国を切拓く山善インドネシアのビジネス戦略と現地で奮闘する若手セールス
- 機械事業部
- 海外
- 営業社員
製造業が抱えるマーケティングの課題とデジマケを成功させる方法
2024.05.31
BtoBでの取引がメインとなりやすい製造業にとって、マーケティングは難易度の高い問題です。企業向けのアプローチ方法に加えて、担当者個人の目を引くアピールポイントも考えなくてはなりません。近年においては、デジマケ(デジタルマーケティング)も考慮する必要があります。
今回は、製造業が抱えがちなマーケティングに関する課題や、デジマケを成功させるコツを紹介します。
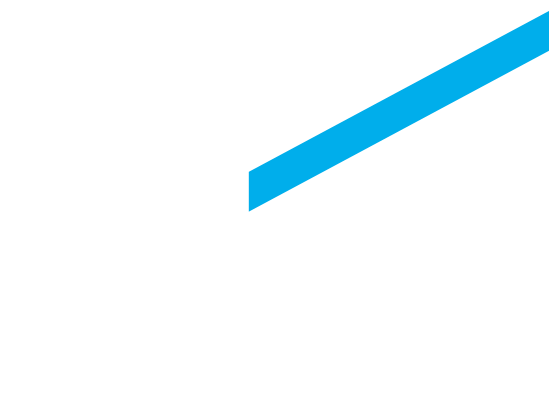
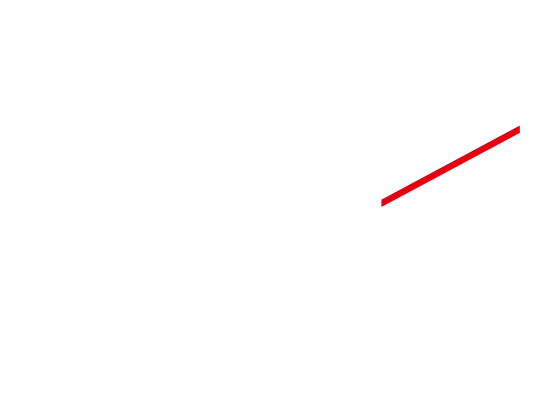
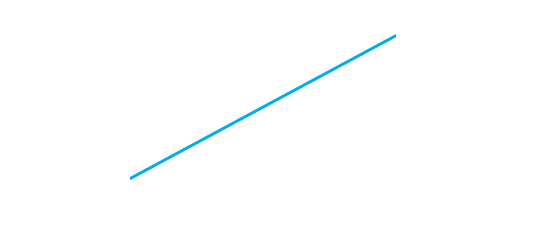
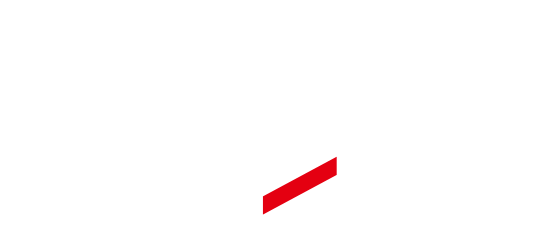
ほかの業種と同じく、製造業においても有効なマーケティング施策を多様に展開することは可能です。
マーケティング戦略を立てるとき、まず考えなくてはならないのが世の中はデジタルに舵を切っているということです。新型コロナウイルス感染症拡大にともない、テレワークが拡大したり、各種展示会もオンライン開催に変更したりするなど、ビジネスのさまざまな場面でデジタルシフトが加速しました。
コロナ禍でリアルの展示会への出展・参加・開催ができず、余った予算を有効活用する手段としてデジマケにシフトするといった企業も増加しました。
2021年に行われたアンケート調査によると、実際、商談につながるチャネルの半数以上がデジマケ由来でした。具体的には、Webサイトからの問い合わせが58%です。
出典:株式会社マーケライズ「製造業界の営業・販促を調査 58%が「ホームページからの問合せは商談に繋がりやすい」と回答 非対面での営業・販促に企業ホームページの改善が有効」
製造業において、新規顧客の獲得を目指すときに有効なデジタルマーケティング施策を3つ紹介します。
■メルマガ配信
まずは、メルマガ配信で問い合わせ数を増やす方法です。メルマガは展示会などであらかじめ配信登録をしてくれた相手にのみ送信し、プロモーション情報を届けます。
ただし、手動で送ると送付規模によっては多くの工数がかかります。顧客に適した内容を用意したり、顧客の状況に応じたタイミングで配信したりすることは困難です。MA(マーケティングオートメーション)を活用して、顧客に合わせたアプローチを行うのもひとつの手です。
■Webを利用したコンテンツマーケティング
2つ目は、自社メディア(オウンドメディア)や動画配信サービス、SNSなど、Webを利用したコンテンツマーケティングの活用です。例えば、製品やサービスに関する解説や使い方、事例などを紹介する動画は、個人のみならず企業向けのマーケティングにも役立ちます。
近年は、オウンドメディアを利用した手法も盛んです。製品に特化したブランドサイトやテーマを絞り込んだWebメディアは、興味関心が高い層の獲得を狙えます。
■製品に関係するポータルサイトへの広告
3つ目は、Web広告を打つとき、製品に関係するポータルサイトへの出稿を意識することです。業界の総合ポータルサイトのほか、製品・技術ポータルサイトや領域別Webメディアなども広告の出稿先として適しています。
業界のポータルサイトに広告を打つメリットは、製品名やサービス名が知られていなくともターゲットへ確実にリーチできることです。
ただし、一部の広告サービスを除いて、広告出稿には相応のコストがかかります。自社のターゲット層を十分に調査した上で出稿先を決めましょう。
製造業がデジマケを取り入れるときのコツは3つあります。
BtoBであってもBtoCであっても、顧客ターゲットが明確でなければ効果的なアプローチはできません。顧客ターゲットを定めるために、下記3つのステップを取り入れましょう。
| 1.顧客ターゲットの分析と設定 | 企業の調達関係者、別の製造業者、趣味での利用(個人)など、ターゲットを分析して、売りたい相手を設定する。 |
| 2.購買フローの確認 | 設定したターゲットがどのような情報収集媒体を利用するか、関心ごとや検索キーワードは何か、データを分析したうえで購買フローを作成する。 |
| 3.顧客の把握 | 購買フローを参考に、顧客が現在どの段階にいるかを把握する。 |
顧客フローマップを作成して、それぞれの段階に合ったアプローチ方法を確立させることが大切です。
自社のターゲット層や目的に合わせて、適切なマーケティング手法を選びます。主なマーケティング手法ごとに狙える効果やメリットは下記の通りです。
| SNS |
・潜在層にもアプローチしやすい ・広告費をかけずに知名度を上げられる
|
| 動画 |
・製品やサービスの特長を視覚的にアピールできる ・実際の使用方法を動画で解説できる
|
| 業界特化ポータルサイト |
・既存登録ユーザーにアプローチできる ・業界の関係者が多く、購入意思決定までの期間が短い
|
上記の効果を引き出すためには、使用するメディアの選び方も大切です。例えば、ポータルサイトは自社に合ったサイトを選ばないとターゲットにリーチしにくくなります。
大前提として、製造業に特化したプラットフォームを選ぶことがポイントです。ただし、業種が合っていればどこでも良いわけではありません。
信頼性が高く、安心して利用できるツールやプラットフォームを選びましょう。プラットフォームの信頼性を調べるコツは、登録企業など利用者に注目することです。また、サービス提供者がしっかりとしたセキュリティ対策をしているかも重視しましょう。
製造業の担当者がマーケティングをデジタルに移行できない理由として、3つの課題があげられます。
製品開発に関するエンジニアを多く抱えている一方で、マーケティング関連の知識をもっている人材や専門部署はゼロという製造業者は多いのではないでしょうか。内製できない場合、専門会社へコストをかけて発注しなくてはなりません。
そもそも製造業は常に人材不足に陥っている場合が多く、Webマーケティングに割ける予算も人的リソースもないのが現状です。
特定の業界をターゲットとするBtoB取引の場合、「自社の製品はニッチだから」と、Web上で検索されるわけがないと決めつけている経営者や担当者もいます。ニッチな製品でも、Webマーケティングが無意味とは言い切れません。
近年は、検索結果から製品や企業サイトに辿り着くこともあります。展示会で知った場合も、事前にWeb上で情報収集してから営業担当者にコンタクトをとるケースも考えられます。
Webマーケティングには、セキュリティの問題がついてまわります。独自技術や顧客情報の漏洩が起これば、企業イメージに大きな影響を与えます。実際、SNSから企業秘密が漏洩した例は少なくありません。
そもそも競合他社や業界に情報公開できない状態でWebマーケティングを行っても、結果につながるか疑問が残るという方も多いのではないでしょうか。
公開できる範囲の明確化やマニュアル整備はもちろんですが、それらに先立ち、コンプライアンスを遵守し、会社全体でセキュリティ意識を共有することが重要です。
製造業において活用可能なマーケティング施策はさまざまです。体制を整えれば、BtoBやニッチな製品がメインの企業であっても成功させられます。
しかし、社内に適切な人材がいなかったり、マーケティングにリソースを割く余裕がなかったりと、課題を抱える企業もいるのではないでしょうか。無理にすべての施策を実施するのではなく、自社にとって取り入れやすいことから始めてみましょう。
効率的に自社の課題解決やPRを行いたいときは、下記3つの機能を有する「ゲンバトエンムスビ」がおすすめです。
1.公募機能:技術的課題を提示すると、解決できる企業とつながれる
2.企業PR機能:営業リソースをかけることなく、自社の技術をターゲットにPRできる
3.営業サポート機能:資料のダウンロード数など、自社の魅力を視覚的に整理できる
自社が抱える課題の解決だけでなく、技術や製品の強みをニーズの強いターゲットにアピールできます。
製造業でマーケティング施策を強化させたい企業は、ぜひご検討ください。