
2024.03.28
- お役立ちコラム
製造業のDXにまつわる課題と対策をわかりやすく解説!
- お役立ちコラム
協働ロボットの市場はどう変わる?需要が伸びている要因を解説
2024.07.01
協働ロボットの市場は業務効率化や品質向上など、さまざまなメリットから拡大が見込まれています。協働ロボットを取り入れることにより、自社でどのような効果が見込めるのか、具体的に知りたい方もいるでしょう。
今回は協働ロボットの将来性や需要拡大の要因、導入事例を紹介します。
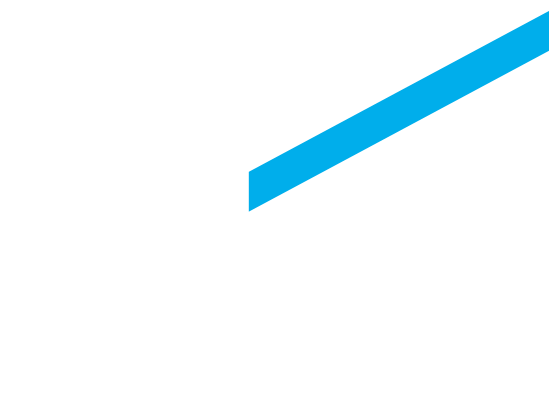
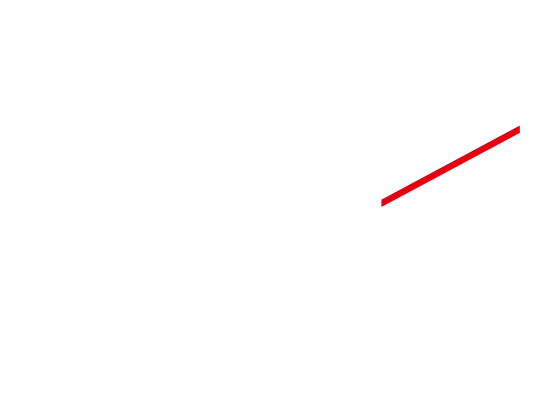
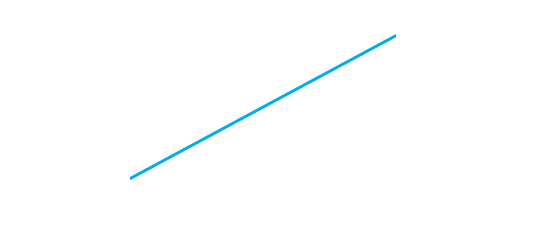
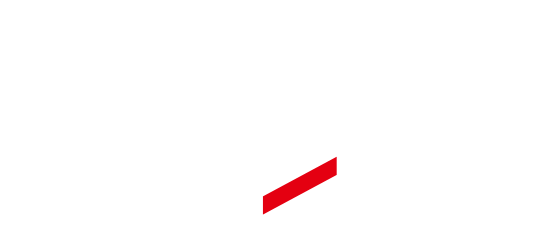
協働ロボットは、今後、生産現場を中心にさらなる活用が見込まれています。そこで、実際に協働ロボット市場がどのような状況にあり、これからどのように発展していくと考えられるのか、その将来性について解説します。
協働ロボット市場は、今後拡大していくことが見込まれています。デロイトトーマツコンサルティングによると、2033年には3兆円規模に迫るとの予測です。また、矢野経済研究所によれば、出荷台数は2032年までに43万台になると予想されています。
協働ロボット市場拡大の背景にあるのが、人手不足や品質向上などを目的とした製造現場の自動化に関するニーズです。協働ロボットは、設定次第で細かい作業をはじめ、さまざまな工程をこなせます。加速していく少子高齢化にともなう人手不足を補う戦力として、今後、ますます導入が進むでしょう。
また、AIの普及にともない、協働ロボットの設定や準備の負担が大幅に軽減できるようになりつつあることも、市場拡大が予想される理由のひとつです。さらに、協働ロボットの導入費用を抑え、使った分だけコストが発生するサービス形態も海外で広まりつつあり、市場拡大の追い風となることが予想されます。
出典:
日経クロステック「人と一緒に働く協働ロボットに導入拡大の兆し、2033年の世界市場は3兆円規模に」
矢野経済研究所「協働ロボット世界市場に関する調査を実施(2023年)」
すでに、ロボット市場は世界的に拡大しつつあります。矢野経済研究所の調査によると、2021年の段階で、協働ロボットの世界出荷台数はメーカー出荷台数ベースで44,204台、出荷金額ベースで1,496億6,900万円です。
世界的なロボット市場の躍進をリードしているのが中国や欧州といった国々です。中国では、国内で協働ロボットの有用性などが理解され、製造業はもちろんのことサービス業などでも導入が進んでいます。欧州では、協働ロボットの世界的なシェアを誇るデンマークのユニバーサルロボットが有名です。
出典:矢野経済研究所「協働ロボット世界市場に関する調査を実施(2023年)」
協働ロボットの需要が伸びている主な要因として、下記の3つがあげられます。
・品質を安定させられる
・レイアウト変更に柔軟に対応できる
・業務効率化を図れる
従業員の手作業では、作業した担当者によって、どうしても品質にバラつきが生じる可能性があります。しかし、現状の作業工程を「見える化」した上で、協働ロボットを導入・活用すれば高い品質を安定して保てます。製品の品質が顧客や取引先からの信頼に直結する製造業では重要なポイントです。
また、協働ロボットは小型でスペースを取りやすく設置場所を選びません。柔軟に配置を変更できるので、生産性や作業効率が高くなるレイアウトに最適化できます。
従業員とは異なり、協働ロボットには稼働時間の制約がないため、生産性の向上が図れます。さらに、もともと作業を担当していた従業員をほかの業務に割り当てられるようになるため、効率化とあわせて生産性の向上も見込めます。ワークライフバランスの改善を図りたい現場にも最適です。
このように、従来のロボットと比較しても、協働ロボットの導入が生産現場に多くのメリットをもたらすことから需要が伸びています。
従来のロボットと比較すると、協働ロボットには主に下記のような違いがあります。
・安全性が高いため一緒に作業ができる
・省スペース設計である
・異なる製品も生産できる
それぞれの違いについて解説します。
協働ロボットは従来のロボットと異なり安全性が高いため、安全柵を設置する必要がなく、従業員と同じ空間で連携して作業できます。安全柵とは、ロボットが動作する範囲に誤って人間が入ってしまわないように設置する囲いのことです。
安全柵を必要としない理由として、協働ロボットが比較的小型であること、人間に接触したら停止するなど安全性を担保する設計になっていることがあります。
人間と一緒に作業できることで、協働ロボットは従業員をサポートする役割を担ったり、従業員の作業を代替したりできます。人手不足を解消したい場合や、軽作業を自動化したい場合などにも対応できるのがメリットです。
従来のロボットは比較的大型であることに加え、安全柵の設置が必要であるため、導入するには大きなスペースを確保する必要があります。しかし、安全対策の施されている協働ロボットは、安全柵の設置は不要でサイズも小型なので、少ないスペースにも設置可能です。
これまでロボットの導入が難しかった作業場にも導入できる上、レイアウトを柔軟に配置できるのが協働ロボットの特徴です。
協働ロボットが複数の製品や部品の生産に対応できるのも、従来のロボットと異なる点です。
従来の産業用ロボットは、特定の用途のために製造されているものが多くあります。しかし、協働ロボットは簡単に設定を変更でき、さまざまな用途に使えます。例えば、異なる品種の製品を少量ずつ生産したい場合でも対応できるのが魅力です。
また、カバーできる範囲が広いことで、1台の協働ロボットを導入すればさまざまな工程に対応できレイアウト変更なども不要なので、費用対効果を高められます。
協働ロボットは、すでに電子部品・自動車・物流・食品・医薬品・化粧品・建設・家電の組み立てなど、多彩な業界で活用されています。
近年では、可搬重量が20㎏を超えるものも多くなっており、50㎏に対応する協働ロボットも開発されています。可搬重量の大きさが特徴である協働ロボットは、下記のようなシーンで運用可能です。
・重量物のパレタイジング
・加工機へのワーク脱着
・事業用トラックのタイヤ搬送
・車載バッテリーの中間組み付け工程
また、アーム部分を敢えて短めにすることで、人間が手元で行う作業への対応力を高めた協働ロボットもあります。このようなショートアームタイプの協働ロボットは、工作機械へのワークの投入や、薬品・化粧品のハンドリングなどに最適です。
特に、防滴性能や防塵性能が高いタイプであれば、水洗いができるので、食品加工に代表される衛生面を重視したい製造現場で活躍します。
協働ロボットは、安全性が高く安全柵なしで運用できるため、従業員と一緒に作業できるロボットです。従来のロボットと異なり、小型でさまざまな用途に使えるため、人手不足を補いたい場合や、これまでロボット導入が難しかった工程の自動化などに役立ちます。
世界的にみても将来性が高い協働ロボットは、導入時の準備にかかる労力の軽減や低コスト化、機種の多様化などにより、導入しやすい環境が整いつつあります。
山善TFS支社の「テックマン」もテストラボにて専門スタッフによるデモンストレーションやワークテスト等のメニューをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。