
2024.04.01
- お役立ちコラム
図面管理を効率化する方法とは。データ化した図面を管理するときのポイントを解説
- お役立ちコラム
製造業における利益率とは?利益率の目安と改善する方法を解説
2024.10.18
利益率は企業の財務健全性のバロメーターとされています。売上高よりも重視されることもある会社経営上の重要な指標です。今回は、製造業における利益率や、利益率を改善する方法について解説します。
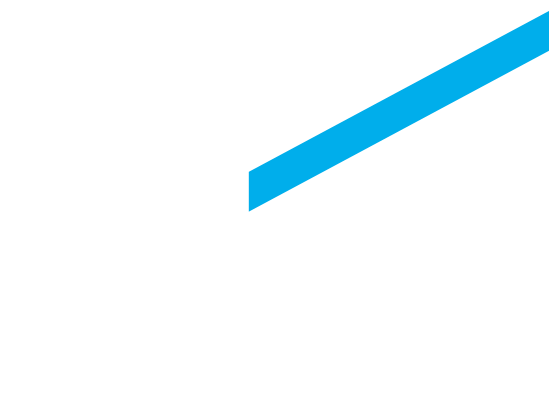
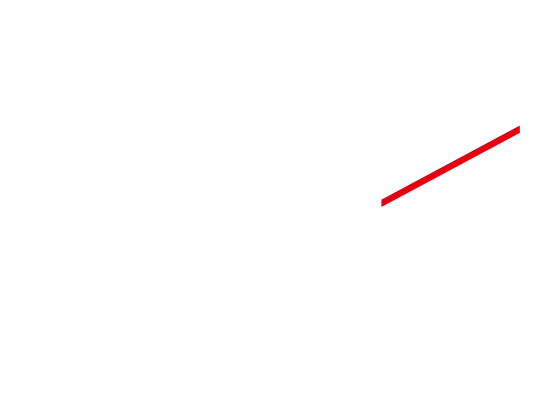
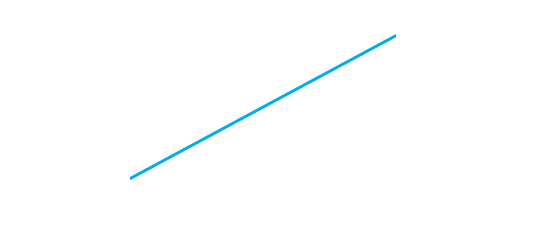
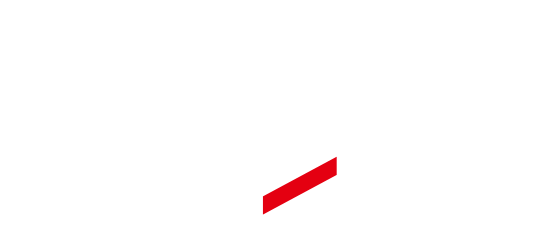
製造業に限らず、利益率は企業の経営状態を客観的に把握する上で非常に重要な指標です。利益率を理解することで、企業の収益性や効率性を評価し、競争力を維持するための戦略を立てることが可能になります。
主要な利益率として、下記の5つがあります。
・売上高総利益率(粗利益率)
・売上高営業利益率
・売上高経常利益率
・自己資本利益率(ROE)
・総資本利益率(ROA)
各数値の計算方法や意味を説明します。
売上高総利益率とは、販売した製品やサービスの利益率のことです。主に下記の計算式で算出できます。
売上高総利益率=売上総利益÷売上高×100
この指標は、製造業において製品の製造にかかるコストの効率を評価するために使用されます。売上総利益は、損益計算書の基本となる利益のことで、粗利益ともいわれます。製造業の場合、「売上高-製造原価」で算出可能です。
売上高総利益率が業界平均や前年度に比べて低い場合、製造コストの上昇や販売数量の減少が考えられます。コスト削減の機会を探るか、製品価格の見直しを行う必要があるといえます。
売上高営業利益率は、売上高に対して営業利益がどれくらいの割合かを表した割合です。計算式は下記の通りです。
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
営業利益は、「売上総利益-販売費及び一般管理費」で求められ、企業の本業により生み出した利益のことです。製造業であれば、自社で製造した製品の売上が営業利益です。
販売費は販売費や広告費など、一般管理費は会社の運営に関わる人件費や本社運営費、租税公課などを指します。製造業の場合、工場など製造に関わる部門で働く人の費用は製造原価に含め、本社で経理業務などを行う従業員にかかる費用は一般管理費として計上します。
売上高営業利益率が低い場合、企業の本業である製造や販売で十分な収益を上げられていないことを意味するため、運営の効率化や戦略的な見直しが必要不可欠です。営業効率の改善や市場戦略の最適化を図ることが収益改善への鍵となります。
売上高経常利益率とは、売上高に対する経常利益の割合のことを指します。下記の計算式で求めることが可能です。
売上高経常利益率=経常利益÷売上高×100
経常利益は、「営業利益+営業外収益-営業外費用」で求められます。営業利益は本業で発生した利益のみですが、経常利益は本業を含むすべての財務活動で発生した利益を表します。
売上高経常利益率が売上高営業利益率よりも低い場合、金融費用など非営業活動からの負担が大きいことを示しています。企業は財務戦略を見直し、借入コストを管理することで利益率を改善することが可能です。
自己資本利益率とは、企業が所有する自己資本で上げた利益がどれくらいかを表す指標です。こちらは下記の2つの計算式で求められます。
自己資本利益率=当期純利益÷自己資本×100
自己資本利益率=一株当たり利益÷一株当たり純資産×100
自己資本は、「純資産-新株予約権-少数株主持分」などの方法で計算でき、返済の必要がない資金のことです。
自己資本利益率が低い場合、企業の経営効率が悪いと判断されるため、利益増加に向けた戦略的な改善が必要です。総資産の回転率を高めることにより、資本の効率的な利用を促せます。
総資本利益率とは、企業が所有するすべての資本でどれだけの利益を得たかを表した指標を指します。計算式は下記の通りです。
総資本利益率=当期純利益÷総資本×100
この数値が低い場合、企業が資本を効率的に活用できていない可能性があります。資産の最適化や投資効率の向上を図ることで、より高い収益性を達成することができます。
経済産業省による企業活動基本調査に基づくデータは、利益率の重要な指標として利用されています。
2022年度の実績調査によれば、全体の売上高営業利益率は4.0%(前年度差0.3%減)、売上高経常利益率は6.7%(同0.2%増)でした。
製造業の売上高営業利益率は4.9%(前年度差0.8%減)、売上高経常利益率は8.7%(同0.3%減) とそれぞれ低下していました。
これらの数字を自社の業績と比較することで、経営の効率性や市場内での競争力を評価することができます。特に利益率の変動を理解することは、投資や経営戦略の調整において重要な役割を果たします。
出典:経済産業省「2023年経済産業省企業活動基本調査(2022年度実績)」
製造業における利益率の向上は、競争が激しい市場で企業が生き残るために欠かせません。ここでは、利益率を高める方法を3つ紹介します。
新規顧客の獲得は売上を直接的に増加させる方法であり、営業利益率の改善につながります。展示会や業界イベントへの積極的な参加、Webマーケティングの推進による認知度アップ、営業チームのスキル向上で顧客ニーズに合わせた提案を強化などが考えられます。
原価を削減し利益率を改善するには、生産プロセスの効率化が不可欠です。具体的には、設備の最新化やITツールによる自動化・省力化などがあげられます。
これらの改善により生産コストの削減だけでなく、生産ロスの低減にもつながります。
生産ロスが生じると、製造にかけた時間や資材、人材、電気代などが無駄になってしまいかねません。生産性向上を図る上では、できる限り生産ロスを低減することが求められます。
生産ロスを減らすには、まずどのような生産ロスが発生しているかを把握することが重要です。
生産ロスの原因となり得る不良の発生を抑えるには「ゲンバト不良記録」がおすすめです。「ゲンバト不良記録」は、不良の発生から改善までのデータをまとめて管理できます。
不良の数量や種類・発生場所・ロスコストなどがグラフ化されるので、社内の品質状況をいつでも把握できます。また、「ゲンバト図面管理サービス」を一緒に使えば、図面に紐づけて過去の不良や改善した内容も一元管理できます。
業務効率化のカギとなるのは、最新のIT技術の導入です。近年、特にERP(基幹系情報システム)が注目されています。ERPを導入することで、リードタイムの短縮や在庫管理の最適化が可能となり、生産性の向上が実現できます。
そのほか、利益率に影響する原価管理の効率化を図ることも大切です。管理の手間を軽減し、原価の見える化を実現するには、「ゲンバト日報管理」がおすすめです。フォーマットに沿って必要な情報を入力するだけで、作業にかかった時間などのデータを集計できます。
さまざまな業務の自動化によりリソース管理がスムーズになると、従業員がコア業務に集中できるようになります。受発注から生産・物流までの業務プロセスを自動化させることは、製造業にとって重要なDX推進の足掛かりとなるでしょう。
製造業の利益率は、企業の経営状態を把握するための重要な指標です。売上高総利益率、営業利益率、経常利益率など、主要な指標を定期的にチェックし、経営課題を発見することで先手を打っていくことが望まれます。