
2024.02.28
- お役立ちコラム
カーボンニュートラルと脱炭素の違いとは?関連用語も解説
- お役立ちコラム
クラウドセキュリティとは?製造業におけるリスクや対策を紹介
2024.05.31
クラウドセキュリティとは、クラウド環境を安全に利用するためのセキュリティ対策のことです。クラウド利用時は、情報流出や不正アクセスなど、考慮しておきたいリスクがあるため対策が欠かせません。今回は、主なセキュリティリスクやセキュリティを高める方法について解説します。
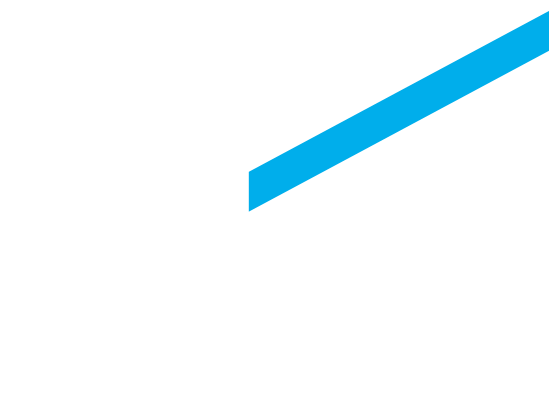
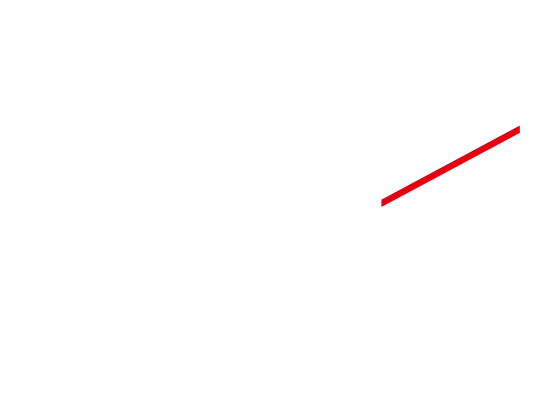
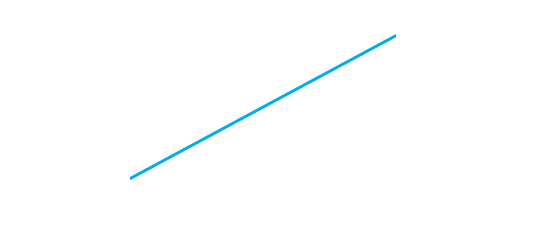
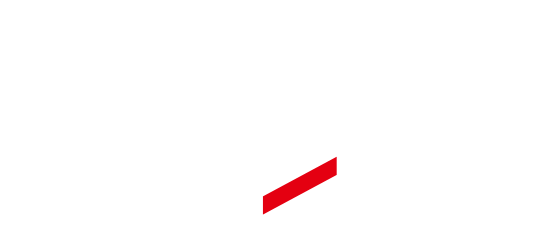
クラウドセキュリティとは、クラウドサービスを利用する際に注意すべきセキュリティリスクへの対策のことです。
クラウドサービスは利便性が高く、DX推進の観点からも有用であるため、製造業のみならず幅広い業種で普及が進んでいます。サーバーなどを自社で保有・管理するオンプレミスと比較しても、利便性やセキュリティ面で引けを取らない上、テレワークなど多様な働き方と相性が良い点も普及が進んでいる要因です。
セキュリティ面を例に挙げると、クラウドには暗号化や不正ログイン検知、パスワード漏れ検知などがあるため安心して利用できます。
オンプレミスはコストをかけるほどセキュリティを強固にできる一方ですべての対策を自社で賄うことが必要です。そのうえ、セキュリティ対策を担う担当者がもつ専門知識にセキュリティの高さが左右されるという欠点があります。
この点、クラウドであれば一定のセキュリティの高さが担保される点がメリットといえます。
ただし、クラウドの利用に関して正しい知識の不足や対策の不十分さによる情報流出などの事故も増加しているのが実情です。
クラウドサービスを安全に利用するには、リスクを正しく把握し、サービス利用者・サービス提供者の両方からの対策が必要です。
クラウドサービスを利用する際に留意しておきたい主なセキュリティリスクは下記の通りです。
・情報流出
・データ消失
・不正アクセス
・サイバー攻撃
各リスクの具体的な内容について解説します。
クラウドサービスでは、クラウドサービス提供事業者のサーバーにデータを保管します。インターネット経由でサーバーにアクセスしてデータを利用する仕組みであるため、IDやパスワードなどが漏洩すると情報が流出するリスクがあります。
製造業では、技術や製品に関する機密情報、取引先・顧客のリスト、従業員の個人情報などの取り扱いに注意が必要です。これらの情報が漏れると、知的財産の流出、個人への実害、社会的信用の失墜につながるからです。さらに、被害状況の調査や被害者への謝罪・再発防止対策に、人的コストや金銭的コストがかかるといった二次被害も考えられます。
利用者の操作ミスや、天災・人災によるクラウドサービス提供事業者のサーバー故障などによって、クラウドに保管したデータが消失するリスクがあります。
重要なデータが消えると、業務の継続に支障をきたしかねません。多くのクラウドサービスはバックアップ機能を備えていますが、利用者側でも速やかにデータ復元できるよう対策しておくことが大切です。
マルウェア感染や不適切な管理体制によりIDやパスワードが流出すると、個人情報の流出やアカウント不正使用による不正アクセスが発生します。
不正アクセスされると、機密情報などを改ざんされるリスクがあります。データの改ざんは、工場で使用する設備・機器・システムにおける誤作動や不具合の一因です。生産ラインがうまく機能しなくなると、取引先・顧客・サプライチェーン全体に影響が及んでしまうこともあるでしょう。
サイバー攻撃によって、工場設備や機器が制御不能・停止してしまうリスクがあります。設備・機器が停止すると、顧客・取引先へ製品を提供できなくなり、大きな損失につながるばかりか、取引停止となるおそれもあります。
注意すべきサイバー攻撃の代表例は下記の通りです。
| DDoS(ディードス) | ・複数の機器から膨大なデータを送信しサーバー障害を引き起こす |
| ブルート フォースアタック | ・IDやパスワードのあたりをつけて大量に試行し盗み出す |
| ランサムウェア | ・工場の設備や機器を元に戻すことを条件に法外な身代金を請求 |
工場システムの総合的なセキュリティに関しては、経済産業省の「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」が有用です。
ここではクラウドサービス利用時に焦点を絞り、下記のセキュリティを高める方法について紹介します。
・データの暗号化
・脆弱性の検知
・データのバックアップ
・ユーザー認証やアクセス制御の強化
・信頼性のあるクラウドサービスプロバイダの選定
クラウドサーバーとの通信や保管時のデータを暗号化すれば、データが漏洩するリスクを抑えることができます。暗号化しておけば、内部不正やサイバー攻撃で不正アクセスされても、データの内容を読み取れなくなるためです。
サイバー攻撃の被害を抑えるには、脆弱性の検知も欠かせません。脆弱性とは、プログラム上の不具合などによってセキュリティが低い箇所のことです。脆弱性をゼロにすることはプログラムの性質上難しいものの、こまめに脆弱性診断を行い、対策を講じることが大切です。
データのバックアップをこまめにしておけば、データが消失したりシステムに不具合が発生したりしても、速やかに復旧して事業を継続できます。バックアップしたデータは、災害時や盗難などに備えて、安全性の高い場所に管理しておきましょう。
不正アクセスを防ぐためには、ユーザー認証やアクセス制御の強化が重要です。ユーザー認証は、「パスワードと生体認証」のようにいくつか組み合わせる多要素認証の導入が効果的です。
また、アクセス制御ではログイン権限を適切に設定し、アクセス可能なIPアドレスの指定も行いましょう。
クラウドサービスのセキュリティ対策の充実度は、クラウドサービス提供事業者によって異なります。そのため、信頼性のあるクラウドサービスプロバイダを選定することが大切です。
提供されるセキュリティ機能や、プロバイダのセキュリティポリシーを確認すれば、安全性の高いサービスかどうかを判断できます。また、クラウドサービスの安全性を証明するセキュリティ基準の取得状況をチェックするのもおすすめです。
| 代表的なセキュリティ基準 | |
| ISMSクラウドセキュリティ認証 | ・ISOによる国際規格
・情報セキュリティマネジメントシステム認証「ISO/IEC 27001:2013」の取得とクラウドサービスセキュリティ管理策「ISO/IEC 27017:2015」の実施で認証 |
| CSマーク | ・日本の特定非営利活動法人日本セキュリティ検査協会(JASA)が実施
・クラウド情報セキュリティ管理基準で定められた要件を満たすと認証 |
ゲンバトは、上記で紹介したISO/IEC27001:2022(JIS Q 27001:2023)の認証を受けている製造業向けクラウドサービスプロバイダです。安全性を担保しながら、製造現場が抱える課題をデジタルで解決します。
製造業に適した安全なクラウドサービスをお探しでしたら、お気軽にお問い合わせください。
クラウド利用には、情報流出・データ消失・不正アクセス・サイバー攻撃など、多くのリスクがあります。しかし、リスクを理解し適切な対策を講じることで、安全に利便性を向上させることができます。まずは、信頼性の高いプロバイダに相談し、安全なクラウド環境を構築できるよう対策を進めていきましょう。